心理職を志す方からご質問いただきました。
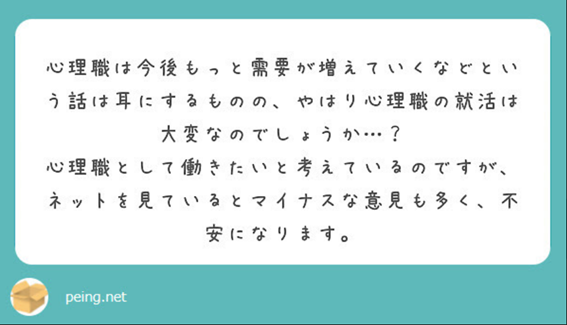
心理職の需要の話は、以前このブログでも書いておりますゆえ、ご興味あればお読みください。
ただ、私は心理職の就活が大変な理由は、単に需要の問題だけではないと思っています。

今回は私が考える心理職の就活が大変になってしまう3つの理由を解説します。
心理職の就活が大変な3つの理由

時間がなさすぎるから
心理職の就活はとにかく時間との戦いです。
一般的な大学生の就活はすごーーーくざっくり言うと
- 大学3年6月インターン応募
自己分析や業界・企業研究など。場合によってはインターン選考のためにエントリーシート・筆記試験・面接対策などをせっせと行います。
- 大学3年8月インターン参加
1~3日間の「短期インターン」や数週間単位の「長期インターン」で自分の適性や業界について理解するよ!(25卒からは政府公認でインターンが採用活動として扱われるので真剣)
- 大学3年9月本選考に向けて本格的な対策開始
インターンを通じて理解した「自分の適性」をもとに志望業界・企業を絞るよ。
- 大学3年3月就活情報解禁・エントリーシート提出
※ただし、就活ルール廃止も検討されているため、今後はスケジュールが変わるかも?
- 大学4年6月選考開始・内定獲得
という感じで、半年から1年かけて行っているのです。
が、心理職の就活はこう!
- 修士2年1月修論提出
たいていボロボロである。
- 修士2年1~3月応募開始・選考
この辺りから心理職の求人が出始めるので、良さそうなところにせっせと応募。場合によってはハローワークを経由しなければならず忙しい。
- 修士2年3月内定
以上!
たった2~3ヶ月程度で就職を決めなければならないのです。
※もちろん、例外はあります。
なぜこんなことになるかというと、心理職の募集がギリギリだから。
心理職はいつでもより良い待遇の仕事を探している生き物。ただ、「今すぐ」という訳ではなく、「やっぱり区切りのいい年度末に辞めたいよなぁ」とぼんやり思っています。
また、公的機関(学校・児童相談所・刑務所など)の非常勤だと「年度末で更新」という契約になっていることも多く、契約更新の話をきっかけに「更新せずに転職してみようかな」と思う人もいます。
そのため、すでに心理職として働いている人は12月頃から転職活動を始めます。そして、その空いたポストの求人が新卒心理職に届くのが1月以降という訳です。

本当にいつどんな求人が出るか分からないので応募タイミングもめちゃくちゃ迷います。
「もうちょっと条件に合った求人があればいいけど、もうさすがに出ないか…」と諦めて2月頭に内定獲得したのに、2月中旬に自分の希望に近い求人が出たときの絶望感は半端じゃない。
このように一般的な大学生が1年くらいかけて行うものを2ヶ月くらいでやるので当然大変です。
もっと早めに始めたいけど、求人もなければ、修論で時間もない…
公務員心理職になる場合は、M2の4月頃に申し込んで、6月頃には試験を受けて8月中には結果が出るので、「早めに安定した職場を得たい!」という場合にはおすすめかも?
倍率は2~6倍と、結構厳しめですが…。
参照元:公務員試験総合ガイド「地方上級心理職の概要」
スキルが求められるのに資格なし状態で挑まないといけないから
心理職って「専門職」なので、就職の条件として「スキルがあるかどうか」が重視されます。
しかし、臨床心理士や公認心理師になれるのは大学院修了後ですから、就活の段階では「資格取得見込み」という状態で挑まなければなりません。
また、大学院で学んだとはいえ実際の経験は乏しいため、もし求人に経験者が応募してきたらかなり厳しい状態になります。(実際、求人によっては「臨床経験〇年以上」なんて条件付きのところも)
その結果、「未経験でもOK」ではあるものの、「人手不足で仕事がハード」で「給与は低め」のところに就職せざるを得ない…ということも少なくありません。
自己アピールが苦手だから
これは人によりますが、大学院で「クライエントの話を傾聴する」を叩きこまれるにつれて、「自分をアピールする」ことに抵抗感を抱きがちになる気がします。
でも、就活は自分を印象付ける場なので、臨床での自分とは少し違う自分を出さないといけません。
また、一般的な大学生は自分をアピールするために
・自己分析:自分の得意・不得意・適性などを理解して、ミスマッチを極力減らす
・エントリーシート対策:要するに自己PRとか志望動機を書く練習
・面接対策:第三者から見た「自分」を意識した言動をとる練習
に取り組んでいる訳ですが、多くの心理職はそういった準備をせずに就活に臨み、撃沈しているのではないかと思います。
なんとなく心理職の就活って「臨床スキルがあれば大丈夫」と思って突撃しちゃいがちですが、やっぱり職場の人としては「この人と長く働いていけるか」を考えるもの。

スキルがあっても、不快にさせられる人とは連携できない。
それは結局、クライエントさんや患者さんの不利益だからね…。
そもそも臨床スキルも15~30分程度の面接でなかなか判断できるものでもないですし…。
なので、「自分はこんなに魅力ある人間です。きっとお役に立てます!」と「あなたの〇〇なところが好きです。就職させてください」という熱烈なアピールを準備しておくのは大事でしょう。
心理職の就職活動対策とは?

先生や先輩とのコネを作る
「いきなりコネかよ」という感じですが、狭い心理の世界では意外とコネはバカにできません。
先生が

このポストが空いたみたいだけどやらない?
と声をかけてくれたり、
あるいは先輩が転職するときに

この仕事、やってみない?
と誘ってもらえるかどうかは、先生や先輩と普段から仲良くしており、そして「この子ならちゃんとやってくれそうだ」と信頼を積み重ねていることが大切です。
どれだけ仲が良くても、臨床力に関して先生・先輩はシビアです。トラブル起こすのが見えている人材を紹介したら、自分の信頼まで傷つきますから真剣です、そりゃ。
大学院の相談室でのケースにしっかり取り組み、ケースカンファレンスでもコメントを真摯に受け止め、研究会や学会にも顔を出し、可能ならポスター発表や口頭発表に参加するなど、とにかく意欲を見せることが大事です。

「仕事への真面目さ」+「社会性」を見せておくってことです。
要するに「リクルーター面談」みたいなもんなんですよね。
就職したい分野や職場をイメージしておく
就職したい領域をイメージした上で、バイトやボランティア先を選ぶのも大事です。新卒の心理職が唯一経験としてアピールできるのはバイトやボランティアだと思います。
でも、療育でバリバリ活躍する心理職になりたいのに、
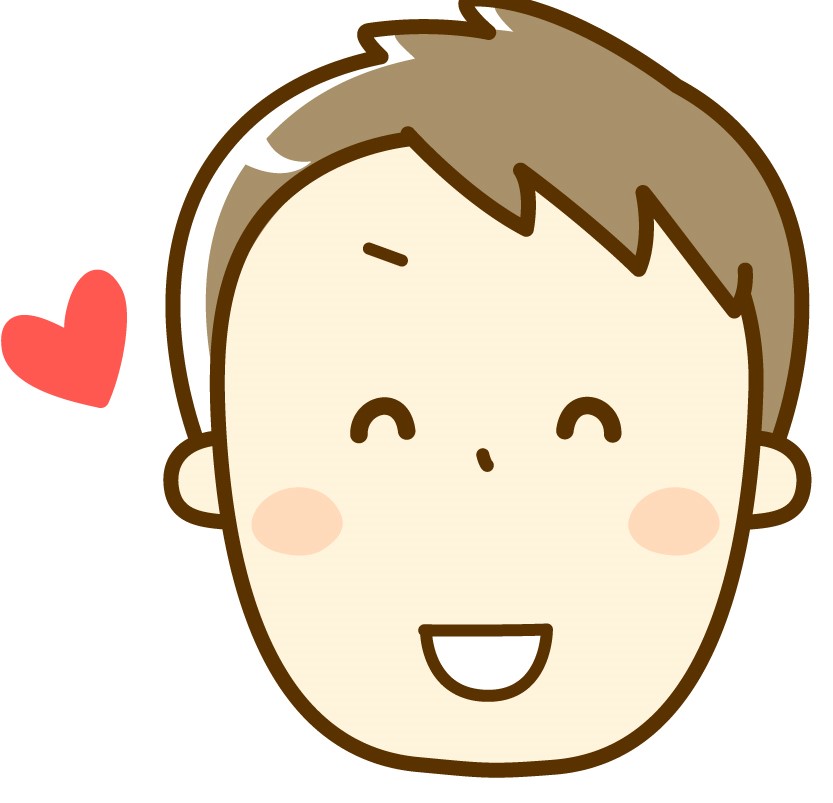
コンビニバイトで、レジでミスしないように頑張っていました!
と、懸命にアピールしても、
え…うん、それで?

としか言えません。
療育分野に進みたいなら、療育施設や児童館、塾や家庭教師など子供と接する機会を得た方が、自分自身も学べることが多いし、「こういう経験を御社で活かしたいです」とアピールしやすくなります。
まぁ、コンビニでも「レジでお客様からの様々なご要望にお応えしつつ、効率良く作業をこなす能力を身につけました。このスキルはたくさんの子供たちに目を配りながら、必要な支援を行う上で活かせると考えています」とか言えなくもない…??うーん?

自分のアピールポイントを知る
心理職のアセスメントって、つい「良くないところ」を見がち。それが自分自身のこととなればなおさらです…が、就活においては「強み」や「長所」を知りましょう。
「自分では分からない!」という人は、先生・家族・友人・Twitterのフォロワーに聞いてみましょう。意外と色々教えてくれるはず。
あとは面接での姿勢とか表情とかも客観的に見てみるのもおすすめ。自分の変なクセを発見できます…。

私は緊張すると足をパタパタするという謎のクセがありました。
意識するだけでも就活の面接時間中くらいは抑えられるので、クセを知るのは大切です。まぁ、就職後はやっぱり足パタパタしちゃうんですけどね。
まとめ

色々書きましたが、心理職の就職って「ジョブ型」の雇用なので、新卒で就職して「ハイ終わり」ではなく、自分のニーズに合ったところにどんどん転職していくものだと思います。
なので、あんまり失敗を恐れず、今の自分が「ここ!」と思うところに就職してみて「ここじゃなかった!」と思ったら転職すればいいや~くらいの気持ちでいいのかなと。

少しでも良い条件・待遇を見つけたら、どんどん挑戦していこう!
ただ、お金がないと「ここを辞めたら生活が…」としがみつかざるを得なくなるので、貯金とか投資とか副業とか、自分の資金に余裕を持たせる方法については、よく考えておいた方がいいと思います。
心理職のお金や副業について知りたい方はこちらもどうぞ↓
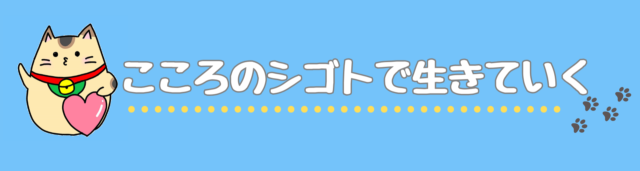
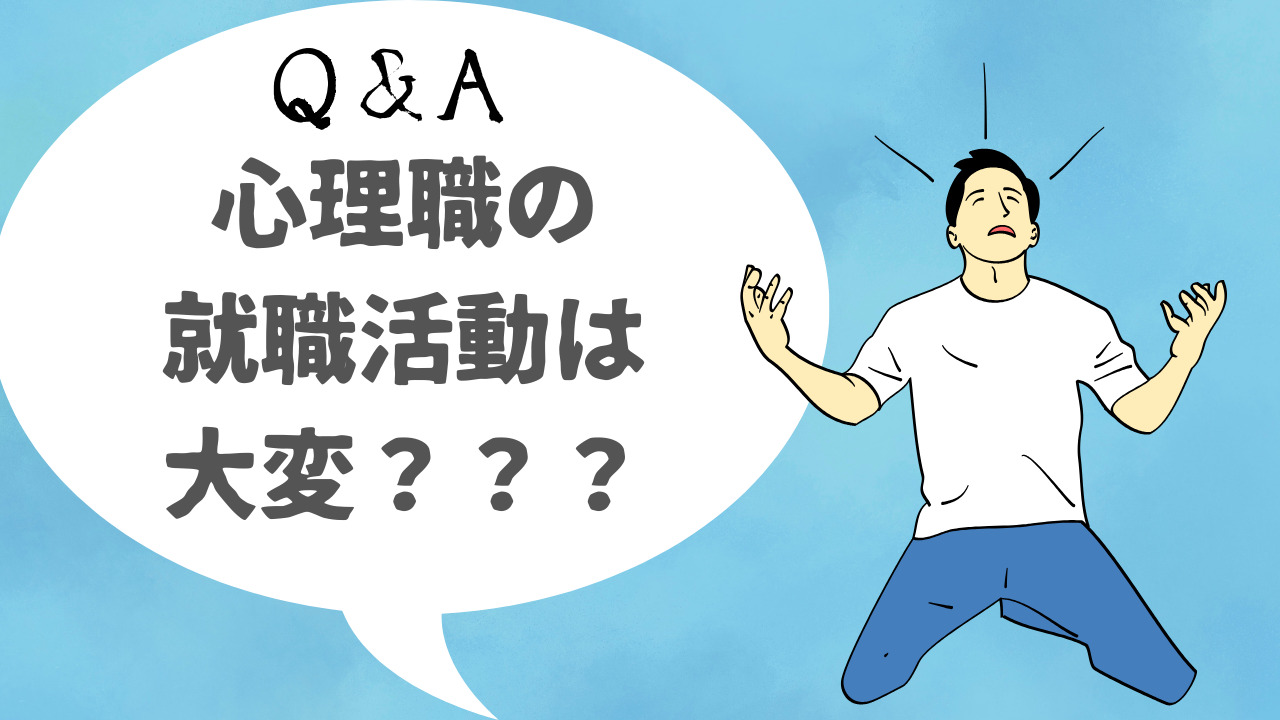

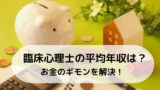
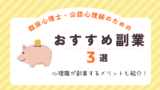
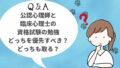
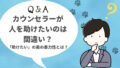
コメント