
将来はカウンセラーの仕事をしてみたい!
カウンセラーと言えば、公認心理師や臨床心理士の資格だけど、
それって必要?働き方に違いは出るのかな?
結論から言えば、カウンセラーに資格は不要!
でも、資格があると働く上で有利になるのは間違いありません
この記事では
・カウンセラーに資格が不要な理由
・資格の有無がカウンセラーの仕事に与える影響
について解説します。
自分がどんなカウンセラーになりたくて
どんな働き方がしたいかイメージしながら
読んでみてくださいね!

カウンセラーに資格は必要?

カウンセラーってよく聞くけれど、
みんな「カウンセラー」の資格を持っているの?
カウンセラーになるのに資格はいらない
カウンセラーとは、専門的な知識を生かして相談を受ける仕事のことを指します。
そのため、カウンセラーと聞いて多くの人がイメージする、メンタル面での悩みに関する相談に対応する「心理カウンセラー」以外にも、
・婚活カウンセラー:結婚したい人たちの相談に対応
・美容カウンセラー:「きれいになりたい」と願う人たちの相談に対応
・キャリアカウンセラー:就職先や働き方に悩む人たちの相談に対応
など、それぞれの専門性を生かしたカウンセラーは多数存在します。
実は「私は心理カウンセラーです」と名乗るために必要な資格や条件はありません。
「今日から心理カウンセラーになろう」と思い立ち、名乗り始めてしまえば、もうあなたは心理カウンセラーになれるのです。
資格がなくても相談を受けることに問題はない
もちろん、資格がなくても
相談を受けることにも問題はありません。


あれ?「公認心理師」って相談業務をしているよね?
国家資格の人がしている業務って他の人はできないんじゃないの?
国家資格には「業務独占資格」と「名称独占資格」があります。
・業務独占資格:資格を持っている人だけが、その業務を行える
(例)医師・看護師など
・名称独占資格:資格を持っている人だけが、その名称を名乗ることができる
(例)保育士・作業療法士など
なぜ業務独占資格と名称独占資格があるの?
例えば、「業務独占資格」である医師は、治療のために人の身体をメスで切ることが許されます。
しかし、知識や技術のない人が同じようにメスを使うと、かえって状態を悪化させてしまうでしょう。そのような危険なく、誰もが安心してサービスを受けられるよう業務が独占されており、資格なく業務を行うと厳しい処罰を受けることになります。
逆に、「名称独占資格」である保育士の業務を保育士だけが独占するとどうなるでしょうか。保育士しか子育てできないとなると、保護者は自分たちで子育てができません。忙しい保護者が祖父母に子どもを預けることも許されません。
そのため、名称は独占されるものの、業務は独占されていないのです。
国家資格である「公認心理師」は、“心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助”が業務の1つとして定められています。
公認心理師が相談の業務を独占すると、親子での相談、友達同士の相談などの一切が制限されてしまうことになります。そのため、公認心理師は名称独占資格に留まっており、今も「相談」については誰でも仕事にすることができるのです。
資格あり/なしでカウンセラーとしての働き方は違う?

じゃあ、今日から早速「カウンセラー」になろうかな?
ちょっと待って!
資格があるかないかで働くときに違いが出ます
その違いはしっかり確認しておきましょう

専門知識の深さは異なる
公認心理師や臨床心理士は定められたカリキュラムに基づき、専門的な知識や学びを深めます。
そのカリキュラムで学ぶ目的の1つは、相談に来るクライエントさんにしっかり対応するためです。しかし、それと同じくらい、カウンセラーとしての自分自身を守ることも大切な目的となっています。
例えば、クライエントさんはいつも穏やかに話してくれる訳ではありません。
精神的に不安定なクライエントさんは、自傷行為や暴力・暴言、自殺未遂など、様々な手段で自分の苦しさを伝えてきます。
正しい知識がなければ、クライエントさんのこういった行動に対応できず、「カウンセラーなんだから受け入れないと」と過剰に我慢して疲弊してしまったり、「もう無理だ」とクライエントさんを見捨ててしまったりと、カウンセラーとしての仕事を続けられなくなってしまうのです。
「心理カウンセラー」は誰でも名乗れるものの、最低限の知識がないと、結局はカウンセラーを続けられなくなるようなトラブルに巻き込まれる危険性があります。
求人に応募できない可能性もある
カウンセラーの求人は「臨床心理士資格」や「公認心理師資格」の保持者や取得見込みの人だけを募集していることもあります。
そのため、「心理カウンセラーとして仕事をしよう」と一生懸命に求人を探しても、応募さえ出来ないことも少なくありません。
特に学校・病院・行政機関など公共性の高い施設で働く際には、臨床心理士や公認心理師が条件となっているケースが多いため、働きたい場所がある人は応募条件を事前に確認しておきましょう。
クライエントさんの相談しやすさが違う
クライエントさんは、1人で抱えていた悩みをしっかり解決してくれる人を探しています。実際にどんな人が会って「信頼できる」と判断してから相談できれば良いのですが、現実には難しいため、せめてホームページなどから「信頼できる」という情報を見つけようとします。
その1つが「資格」です。全く資格を持たないAさんと「臨床心理士歴10年」というBさんとでは、やっぱりBさんの方が「解決してくれそう」と感じやすいのです。
資格がないままカウンセラーとして働いていく場合には、
・SNSを活用して宣伝する
・YouTubeでメンタルヘルスの役立つ知識を配信する
・カウンセラーとしての実績を積み、口コミを書いてもらう
などの方法で、「この人に相談すれば解決しそう」と感じてもらえるよう工夫することが必要です。
まとめ
ここまでの話をまとめてみましょう!

カウンセラーになるのに資格は不要ですし、資格がなくても相談を受けることに問題はありません。
しかし、資格がないと、カウンセラーの仕事において、
・専門知識が浅く、自分を守れない危険性がある
・求人に応募できない可能性もある
・クライエントさんから信頼を得られにくく、相談に来てもらいづらい
といった不利な面があります。

資格がなくてもカウンセラーはできる・・・
でも不利な面もあるし、私は資格を取ろうかな
カウンセラーの資格もたくさんありますので、
資格を取得するときには
・何が学べるのか
・何ができるようになるのか
もよくチェックしておきましょう

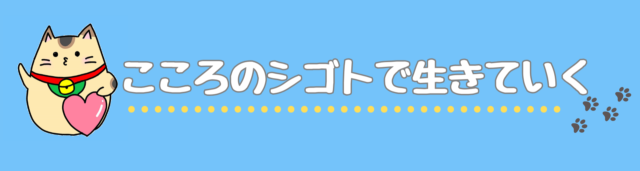



コメント