スクールカウンセラーとして勤務していると、自傷行為をする子によく出会います。
私は、自傷行為は基本的に「してもOK」というスタンスです。
それは、自傷行為は「生きよう」という姿勢の表れだと思うから。
今回は私がスクールカウンセラーとして自傷行為とどう向き合っているかをお話しします。
スクールカウンセラーと自傷行為

スクールカウンセラーが出会う「自傷行為」とは
自傷行為とは自分で自分を傷つけること。
・リストカット(手首を切る)
・アームカット(腕を切る)
・髪の毛を抜く
・唇の皮を剥く
・爪を噛む
・頭や体を思いっきり叩く
・頭を壁にぶつける
など、様々な方法で自分を傷つけます。

過剰服薬(OD)や摂食障害も、自傷行為の一種と言えるかもしれません。
自傷行為の意味
自傷行為には様々な意味がありますが、スクールカウンセラーとして出会う子に多いのは「自分1人で大きすぎるストレスに対処しようとした結果」なのだなぁ…ということ。
「他人に迷惑はかけられない」という真面目な子や、「他人なんて信じられない」と思っている子など、理由は色々あるけれど、とにかく「自分で何とかしよう」と考えている子が、自分なりに編み出した「生き残るための方法」という印象があります。

このほかにも「自己刺激」や「注目を集める」など、様々な目的で自傷行為は用いられている場合があるため、十分に見立てる必要があります。
自傷行為を止めるべきか否か
私は「自傷行為をやめなさい」ということに意味はないと思っています。
自傷行為をしている子は、学校では割とニコニコしていて、真面目で良い子が多いように感じます。なので、つい大人は「やめなさい」と指示すれば、それで大丈夫だろうと思ってしまいがちです。
しかし、実際には当たり障りのない良い子を演じなければならないくらい、世界を信じていない子がほとんどなんじゃないかな…と思います。
「やめなさい」の指示は自傷行為をしている子に「やはり世界はしょうもない」「結局誰も助けてくれない」と確信させるだけで、何の効果もありません。もっと隠れて自傷をするだけです。
先ほどもお話しした通り、「ストレス対処法として」にせよ、「自己刺激」や「注目を集める」にせよ、自傷行為にはちゃんと目的があります。
もし、やめさせるのであれば、代わりとなる方法をきちんと提供しないと、子どもにただただ苦痛や欲求不満を耐えさせる…というだけになります。
これを支援と呼ぶのなら、支援者は本当に楽な仕事です。という訳でそんなものは支援とはいいません。
ストレス対処法として自傷行為に及んでいるのであれば、環境を調整したり、社会資源を活用したり、コーピング方法を増やしたりと、自傷行為が必要なくなるようにサポートしていく必要があります。
「注目を集める」ことを目的としているなら、大人はもっと普段からその子を気にかける必要があるでしょう。また、子どもの側にも適切な注目や承認の求め方を伝えることもありえます。
ただ、「自傷行為はやめよう」「親からもらった身体に傷をつけてはいけない」なんていう言葉は、空虚なだけです。
スクールカウンセラーが自傷行為とどう向き合うか
私は先生から「自傷行為をしています」と申し送りがあれば、来てくれた子に「先生から自傷行為しているって聞いたけど、どんなやつ?リスカ?アムカ?」と直球で聞きます。
そして、できたら傷も見せてもらいます。自傷行為はその子が1人で抱えてきた心の傷だと思うので、少しでも分かち合えたら…と思うのです。
もちろん、無理強いはしませんが、大体の子は「いいですよ」と見せてくれます。なんとなく「誰かには知ってほしい」と思っていたのかなぁ…と感じます。

リスカしている子がSNSで「病みアカ」を作って、自傷したことを書いているのも、「自分を傷つけてくるような人には知られたくない」と「自分を分かってくれる人、自分を傷つけない人に知ってほしい」の両方の気持ちを持っているからだろうな…と思います。
だからスクールカウンセラーはリアルにいながら、「傷つけない人」としてそばにいる必要があります。
自傷行為をタブーにせずに「何で切ってる?カミソリ?カッター?」「いつやったとか覚えている?」「切った後ってどんな感じ?痛い?スッキリ?」など聞いていき、自傷行為のトリガーや解離状態などを把握していきます。
また、「リスカは今はやめたい感じ?もうちょっと続けたい?」なども確認していきます。
すると「まだやめるのは無理かなぁ」という場合もありますが、「傷が残るからやめたい」「修学旅行のお風呂で見られたら嫌だからやめたい」と本人から「やめたい気持ち」が語られたりします。
それでやっと「あなたの自傷は1人でつらい気持ちに対処しようと頑張った結果だと思う。本当によく頑張ってきたね。つらい環境を変えたり、1人じゃなく他の人と一緒に取り組んだりすれば、自傷行為をする必要がなくなるかもしれない。どこから変えられるか一緒に考えよう」と、やめる方向へ進めて行けます。
進め方も本人の気持ちに寄り添いながら、少しずつ少しずつ進めます。世界への信頼がないのですから、手を繋ぎながらおそるおそる進んでいけばいいのです。歩き始めの1歳児の手を引いて猛然と進んでいく人はいないでしょう。
子どものペースでゆっくりゆっくり進むのです。
最初は「誰にも言いたくない!」と言っていても、じっくり話すうちに「〇〇先生ならいいよ」と和らぐ場合もあります。
いきなり、こちらから「自傷行為はダメよ」と言えば、そこで関係は終わりです。
その子はその場では「分かりました。やめます」と言うかもしれません。ただ、スクールカウンセラーを去った後、もう二度と来てはくれないし、大人も信じられなくなってしまいます。
スクールカウンセラーが自傷行為を知るために

半田一郎先生「自傷行為を知ったときの聴き方 受け止め方」金子書房
スクールカウンセラーとして多くの子ども・保護者・先生を支援してこられた半田先生の自傷行為に関する連載コラムです。
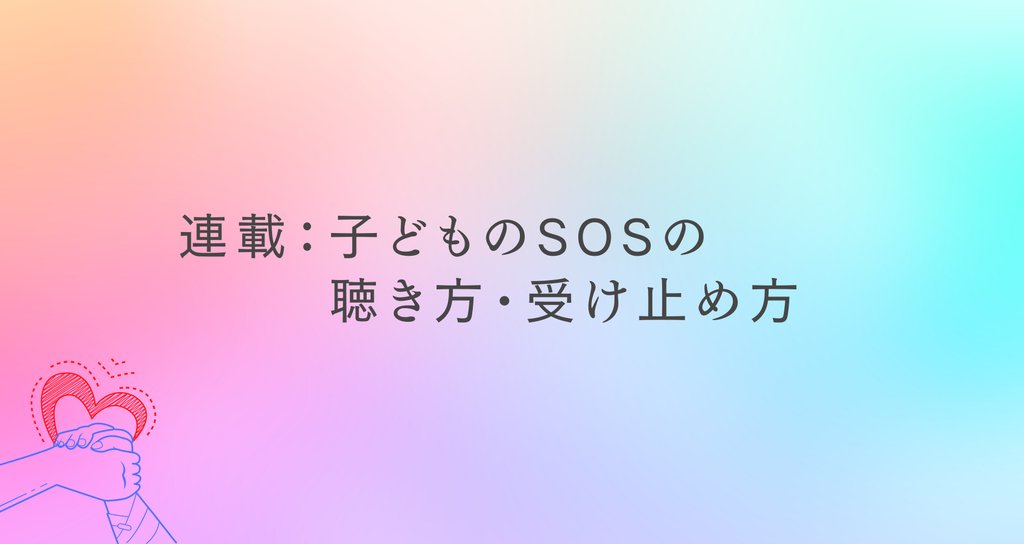
特に【第2回】と【第3回】は、自傷行為へのアプローチがかなり具体的に学べます。【第4回】からは、今回のブログで触れなかった自傷行為への具体的な支援についても知ることができます。ぜひ一読していただきたい内容です。
自傷行為の話題から離れてしまいますが、半田一郎先生の本はこちらもおすすめ↓

・廊下でほんのすこし声をかける程度の10秒
・ちょっとした立ち話程度の30秒
・少し対話できる3分間
という短い時間で、子どもや保護者の心に種をまく事例が掲載されています。
時間が短いからこそ、その一言にあらゆる要素がぎゅっと詰まっている…!
まさに「霹靂一閃」みたいな技を習得できる本です。
松本俊彦先生「自傷行為の理解と援助」
日本精神神経学会学術総会の教育講演がまとめられたものです。
「自傷行為とは何か」「なぜ自傷行為は繰り返されるのか」などを丁寧に解説すると共に、私たちがどのように自傷行為を援助していけばいいのかが8つの視点から詳しく解説されています。
「支援者も1人で抱え込んではいけない」という見逃しがちなポイントや、相談に来た子によく言われる「親には言わないで」への対応なども具体的に記載されています。
松本俊彦先生は自傷に関する様々な本を執筆されています。
こちらの本は「自傷行為をしてしまう人の気持ちをもっと理解したい!」という方におすすめ!自傷行為をする人にどうやって寄り添えばいいかも感じ取れます。
まとめ

自傷行為は「生きるため」の手段だと私は思っています。
そして、スクールカウンセラーをはじめ、支援者は「生きること」を支援するために存在すると思っています。
だからこそ、生きるための自傷行為を簡単に取り上げてはいけないのではないでしょうか。
生きようとする姿勢に敬意を払いながら、その子の人生をより良くするために一緒に歩んでいくのがスクールカウンセラーの仕事だと思います。
スクールカウンセラーが「死にたい」と自殺念慮を訴える子どもにどう対応するかについては、以下のブログをぜひお読みください。
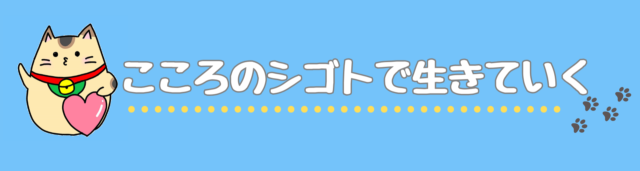

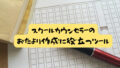

コメント